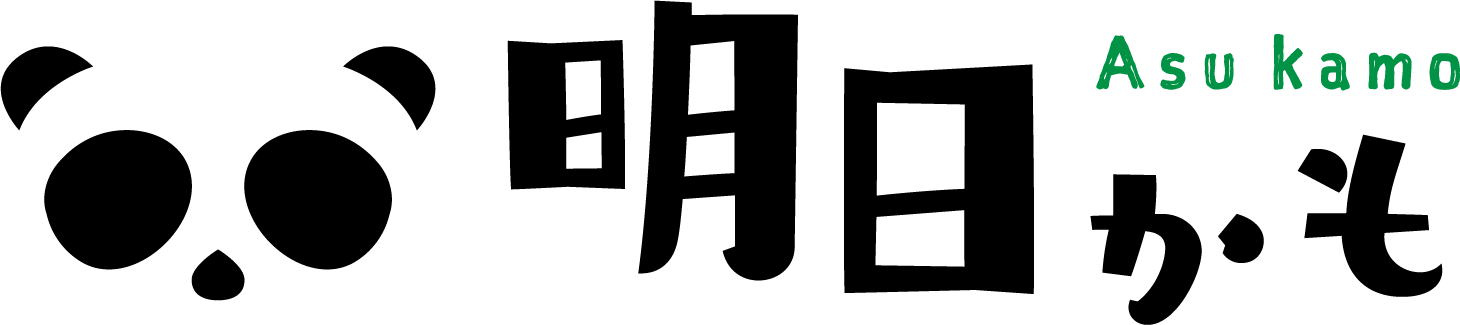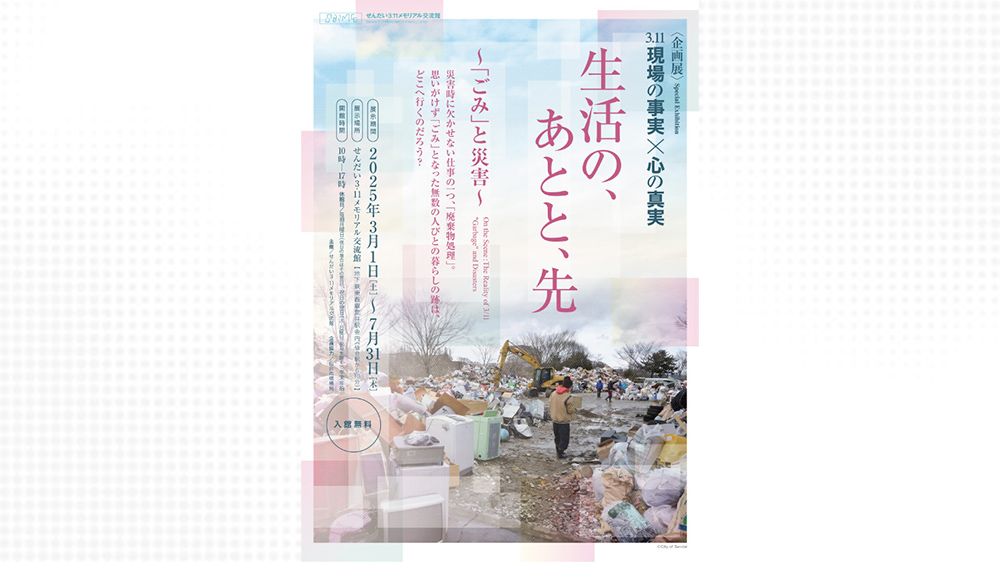こんにちは。皆さんは、災害時にどのような備えをしていますか?
近年、地震や豪雨などの自然災害が多発しており、「もしものとき」のために備蓄をはじめとした防災対策がますます重要になっています。そこで今回は、企業や地域、家庭での防災力を高めるために役立つ資格をまとめてご紹介します。
1. 防災士(民間資格)
概要
防災士は、日本防災士機構が認定する資格で、災害時の適切な対応やリーダーシップを身につけることを目指します。地域の自主防災組織や企業での防災リーダーとしても活躍できるため、自治体などが取得を推進しているケースもあります。
取得方法
- 指定の研修機関で防災士養成研修講座(2日間程度)を受講
- 防災士資格取得試験に合格(3択式30問、80%以上正答)
- 消防署や日本赤十字社などが主催する救急救命講習を修了
費用の目安
- 研修料:約5万円
- 試験・登録料:合計8,000円前後
- ※別途テキスト代などがかかる場合もあります
活用例
- 地域防災リーダーとしての避難訓練指導
- 企業・学校の防災担当者としてBCP(事業継続計画)の策定や運用
- 防災イベントや地域活動への参加
2. 災害備蓄管理士(民間資格)
概要
企業や行政などの備蓄管理を専門とする資格です。災害時に必要な物資の種類や管理方法を学び、オンライン試験で取得できます。
取得方法
- IBT(オンライン)方式で受験
- 公式テキストを学習し、試験(40問+小論文)に合格
費用の目安
- 受講・試験料:11,000円
- 認定登録料:22,000円
役割
- 災害時の物資調達・管理計画の策定
- 企業やマンションなどの備蓄品ローテーション指導
- 事業所のBCP策定における備蓄管理担当者
3. 防災備蓄収納プランナー(民間資格)
概要
家庭やオフィスでの防災備蓄を「収納」の観点から支援する資格です。2級・1級・マスタープランナーの3段階があり、段階に応じて学べる内容が異なります。
2級プランナー
- 内容:基礎講座で備蓄リスト作成や収納設計、ストック管理のポイントなどを学びます
- 取得方法:基礎講座を受講するだけで取得可能(試験なし)
- 費用目安:オンライン講座で約3万円程度
1級プランナー
- 内容:2級の内容に加えて、より専門的な防災知識・収納設計を学び、課題提出+試験に合格すると取得
- 取得方法:2級取得後、2日間の専門講座を受講し試験合格
- 活躍例:家庭や事業所向けに具体的な防災収納プランを提案
マスタープランナー
- 内容:2級講座を教える認定講師として活動できるレベル。防災備蓄収納の普及活動に取り組めます。
4. 職場備蓄管理者(民間資格)
概要
職場の防災備蓄を「継続的に管理する」ことを目的とした資格です。企業の総務担当者や防災責任者向けに、備蓄品の定期点検や廃棄防止策、災害食の管理方法などを学びます。
取得方法
- 認定講座を受講すると資格取得(更新不要)
活用例
- 従業員のための備蓄品管理を担当
- 防災マニュアルの整備や社内向け研修の実施
5. 備蓄防災食調理アドバイザー(民間資格)
概要
災害時の食事や栄養管理に特化した資格です。長期保存が可能な備蓄食材を使ったメニューや衛生管理などを指導できます。
取得条件
- 防災共育管理士3級の修了が必須
内容
- 備蓄食料の衛生管理や栄養バランス
- 在宅避難時の1ヶ月分備蓄の計画策定
- 調理法やディザスタ栄養の考え方などを学習
6. 防災管理者(国家資格)
概要
防火管理者資格を持つ方や、企業の防災責任者が取得を検討する国家資格です。防災管理講習や防火・防災管理講習を修了することで取得可能で、事業継続計画(BCP)の策定や従業員の避難誘導を担います。
7. その他の関連資格・トレーニング
- FEMAトレーニング(米国):地域の消防・緊急サービス向けにリーダーシップスキルや危機管理を学ぶプログラム
- アメリカ赤十字社の災害救援トレーニング:シェルター運営、メンタルヘルス支援などの無料コース
資格選択のポイント
1. 目的・役割を明確にする
- 地域の自主防災リーダーとして活動したい → 防災士
- 企業の備蓄管理を専門的に行いたい → 災害備蓄管理士や職場備蓄管理者
- 家庭やオフィスの収納に着目した防災対策 → 防災備蓄収納プランナー
- 食事や栄養面から災害時をサポート → 備蓄防災食調理アドバイザー
2. 費用・期間
- オンラインで簡単に取得できるものもあれば、数日間の研修が必要なものもあります。
- 費用は数万円かかる資格が多いため、予算と照らし合わせることが大切です。
3. 更新の有無
- 防災士や災害備蓄管理士など、基本的に更新不要の資格が多めです。
- 一部資格は継続学習が推奨される場合もあるため、公式サイトなどで確認しましょう。
4. 興味・関心
- 防災と言っても、救命・食事・収納・備蓄管理など多岐にわたります。
- 自分が特に関心を持てる分野を選ぶと、学習も継続しやすくなります。
まとめ
防災や備蓄に関する資格は、単なるスキルアップやキャリアアップだけでなく、家庭や地域、そして企業の防災力向上に大きく貢献できます。
「自分や家族を守りたい」「職場の防災体制を整えたい」「地域で頼られる存在になりたい」など、目指したい姿に合わせて資格を選ぶことで、より充実した防災活動ができるはずです。
災害はいつ、どこで起きるか分かりません。備えあれば憂いなし。みなさんもぜひ、自分に合った資格を活かして防災力を高めてみてください。